第53回メールゼミ
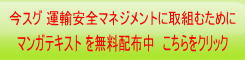 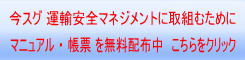
当メールゼミでは、
国土交通省で作成された
「運輸安全マネジメント ガイドライン」の解説を行う
ガイドラインメールゼミをお届けしています。
今回は第3回目です。
ガイドラインとは、
国土交通省大臣官房運輸安全監理官が作成した
「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」
(平成22年3月改訂)のことでしたね。http://www.mlit.go.jp/common/000110883.pdf
今回は、「ガイドラインの適用範囲」です。
当該内容を読みますと、
「3.ガイドラインの適用範囲」という個所に
「本ガイドラインは、事業者の経営管理部門が行う
当該事業の輸送の安全を確保するための管理業務
(以下「管理業務」という。)に適用する」
という記述があり、
解釈によっては、
「運輸安全マネジメントは
経営管理部門が行う管理業務だけが対象なのか?」
との理解をしてしまう可能性がありますが、
「運輸安全マネジメント」は
全社を挙げて取組むことであり、
決して経営管理部門だけの取組みでは
成果をあげるうえで限界がある事を認識する必要があるでしょう。
実際、「ガイドライン」にも
全社を対象にした取組みを要求する記述が多々あります。
では、なぜ、
「ガイドライン」に前述のような記述されているのでしょうか。
本来の記述の意図として、
私は
「運輸安全マネジメントの運用を経営管理部門が行う」
という意味と理解しています。
このように理解はしていますが、
「運輸安全マネジメント」は、
「経営管理部門だけが運用するものではない」
ということをご理解くださいね。
あくまで、経営管理部門は、
「運輸安全マネジメントのオペレーションを行う」
と、ご理解ください。
このことは、或る意味、当然であり
だからこそ、
「運輸安全マネジメント」
とう名称であり、
かつ、
「マネジメント」
という文言が入っているのですね。
他には、
事業者として明確にすべき項目が
次の3点挙っています。
1 経営管理部門の範囲
「経営管理部門」の具体的対象を
明確にする必要があります。
「経営管理部門」とは、
「登記上の取締役」を指すのか
「経営層」を指すのか、若しくは、
「管理者層」を指すのか。
2 経営管理部門が行う管理業務の実施対象となる範囲
これは、
「管理業務」とは、
ナニを指しているのか明確にすることですね。
また、管理業務のターゲットを明確にする必要性も
あるのでは? とも読み取れますね。
これが、日本語表現の難しさで、
ISO9001等であれば、
原文の英文を見ると判るのですが、
「ガイドライン」の場合は、
これこそが「原文」ですから、
意図が伝わり難い個所もありますね。
3 管理業務について、その一部を外部委託する場合は、
当該外部委託した管理業務に適用される管理の方法と
その取組み内容
これは、管理業務の一部を
外注やアウトソースする場合は
その委託した管理業務の方法や内容を
明確にすることですね。
また、外注先(アウトソース先)に対する
管理方法も明確にすべきと
私は理解しています。
この辺のことは、
ISO9001(JISQ9001)の
「4.1一般要求事項」に
同様の規定がありますね。
やはり、運輸安全マネジメントは、
ISO9001を参考に策定されたのですね。
ISO9001に触れたついでに
ISO9001主任審査員として
一つ、付け加えさせてください。
JISQ9001の
「4.1一般要求事項」の
「注記3」には、
次のように規定されています。
「アウトソースしたプロセスに対する管理を
確実にしたとしても、すべての顧客要求事項及び
法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が
免除されるものではない」
この規定内容については、
敢えて、解説は控えます。
ただ、非常に判り易い規定内容だと思いますが、
意味が良く判らない方は、
よーく考えてみてください。
(エラそうでごめんなさい:でも、良く考えてみて!)
今回は、ここまでにしますね。
最後までお読みただき感謝です!
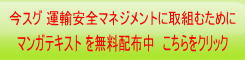 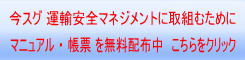
|

