第46回運輸安全マネジメントメールゼミ
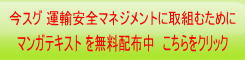 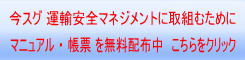
前回から
「文書管理」にはいりました。
この「文書管理」。
簡単なようにみえて、じつは、大変奥が深いのです。
そのことも前回、説明しましたね。
「文書管理」とは、要するに、
「必要なところで必要なときに必要な文書が使用できること」
と説明しました。
今回から、具体的な方法を確認していきましょう。
その1 誰が作成し、誰が承認するのか?
作成すべき文書ごとに「作成者」と「承認者」を
決めておく必要があります。
その決められた「作成者」以外のヒトは、
勝手にその文書を作成したり、改訂してはいけません。
例えば、
「運輸安全マニュアル」の「作成者」以外のヒトが
勝手に改訂してしまったら、
日々の運用が曖昧になってしまいます。
「承認者」も然りです。
当然ですが、「作成者」は、
該当文書を作成する力量があるヒトですよね。
そして、「承認者」は、
その文書の内容を確認して、問題ないことを
承認する力量がある方ですね。
その2 一度作成した文書はそのままにしない
これはどういうことでしょうか?
社内文書として作成した文書は、
一度作成し、その後、何らかの改訂を意図的に行わない場合は
そのまま使用されますよね。
でも、チョット待ってください。
「文書」というのは、指示が入っているモノですよね。
「○○してください」とかですね
例えば、「運輸安全マニュアル」では、
「毎年、4月に目標を立案する」のような
指示が規定されていますね。
その内容が、現時点の自社の状況と照らし合わせて
問題ないのかを確認しなくてはなりませんね。
こまめに改訂されている文書でしたら良いのですが、
改訂が行われていない文書については、
最低でも一年に一回くらいは、
現在の文書内容に問題が無いのかを確認しなくてはなりません。
その3 現在有効な「版」を明確にする
文書も改訂を重ねていくと、
現在、使用して良い「版」が第何版なのか?
それを明確にする必要があります。
例えば、
「運輸安全マニュアル」が第4版として
2011年9月1日に改訂されたのであれば、
現在、有効な版(使用すべき版)は、
第4版ですよね。
まちがって、第3版で仕事をしてはいけないのです。
その4 どこを変更したのか明確にする。
第3版から第4版に改訂された場合、
どの個所が改訂されたのか明確にする必要があります。
明確にする方法としては、
いろいろありますが、
「改訂履歴」に全ての改定個所を明記する方法や、
改定個所を識別する方法があります。
今回は、ここまでにしましょう。
最後までお読みいただき
ありがとうございます。
|

