第43回メールゼミ
前回は、
原因追究を重ねていくと
その先は・・・・・
ということでしたね。
今回は、
原因追究後の活動を考えてみましょう。
前回までで
なぜ原因追究したのか?
それは、
事故という問題を発生(再発)させないためですね。
事故につながる原因を追究し
それを取り除く処置が
予防処置や是正処置(再発防止)でしたね。
ここまでの作業で、
いろいろな
“リスク”に対して
“原因追究”をしました。
その
“原因追究”の結果、
有効と思われる
“予防処置や是正処置(再発防止)”を
洗い出したことになります。
そこで、次の着眼点が必要です。
1 その“予防処置や是正処置(再発防止)”の実施容易度
2 “予防処置や是正処置(再発防止)”を実施した結果、得られる
効果
(これと同じようなこと以前、説明しましたね。覚えていますか?)
この二つの観点から、
実施すべき“予防処置や是正処置(再発防止)”の
優先順位を決めていきましょう。
例えば、
次の二つの事例で考えてみましょう
例1
リスク:目視による左側が確認し難いため左車線変更時に事故の
可能性
原因:助手席のカーテンによる目視不良
対策:助手席カーテンの撤去
例2
リスク:ホーム後退時に接触の可能性
原因:車輌後部の視界不良
対策:バックアイカメラの搭載
まず、
“1 その“予防処置や是正処置(再発防止)”の実施容易度”を
考えてみますと
“例1”はとても簡単ですね。
助手席のカーテンを取り除くだけですから。
それに対して、
“例2”は、
“取り付け”という手間と
費用がかかります。
この場合、“例1”を優先すべきと仮定します。
次に
“2 “予防処置や是正処置(再発防止)”を実施した結果、
得られる効果”を
考えてみると
“例1”は、重大事故を起こす可能性の低減ですね。
“例2”は、物損事故を起こす可能性の低減ですね。
ここでも
“例1”を優先すべきと仮定します。
結果、二つの着眼点により
“例1”の対策を優先させることが必要となるのです。
ただ、“例2”の
“2 “予防処置や是正処置(再発防止)”を実施した結果、
得られる効果”が
“物損事故”ではなく
“子供を刎ねてしまう可能性の低減”でしたら、
少々、解釈が異なりますが(ぜひ発生防止をすべきですから)。
当然、リスク管理の考え方も考慮しましょう。
今回はここまでにしましょう。
次回は
優先順位決定後の展開について説明していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
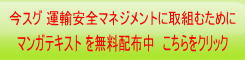 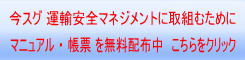
|

