第39回メールゼミ
お元気ですか?
今回からメールゼミは
分類・整理したリスク情報のアプローチ方法です。
まず、分類・整理したリスク情報の
“根本的な原因の分析を行う事象”を
決定するための、
二つのアプローチ方法を説明してみましょう。
一つ目は、ごく一般的なアプローチ方法です。
分類・整理した“事故”“ヒヤリ・ハット”情報のうち
次の着眼点で“根本的な原因の分析を行う必要がある事象”を
決定してください。
A 発生の可能性
B 発生した場合の結果の重篤性(起きた場合の影響)
C “A”と“C”の総合評価
この方法は、“リスク管理”における
“リスクの洗い出し〜評価”の考え方であり、
OHSAS18001(労働安全マネジメントシステム)や
ISO14001(環境マネジメントシステム)の
考え方ですね(ISO14001の場合は環境側面の洗い出し手法
ですが)。
二つ目は、
前回のメールゼミでも少し触れました、
層別によりデータを分類し品質管理七つ道具のうちの一つである
“パレート図”を用い優先的に対応すべき事象を
“根本的な原因の分析を行う事象”と位置付ける方法です。
(品質管理の手法が必ず必要ということではありませんし、
七つ道具のうち“パレート図”を必ず使用するということではあり
ません)
“根本的な原因の分析を行う事象”を
決定したら、その“事象”の原因を追究しなくてはなりません。
“原因追求”については、
あなたはそれほど大変だと思っていないでしょうし、
今まであなたが関わってきた業務の中で問題が発生した場合の
“原因追究”に問題があったとも
思っていないのではないでしょうか。
私もこのメールゼミの読者層が、
以前、ISO専門誌に連載した時のように
“品質管理専門家”であれば
このような考えようによっては“失礼な”ことは
書かなかったのですが、
「製造業の品質管理に関わってきた以外の方」にとっては、
“原因追究”をそれほど重要だと
認識されていない方が多いように思います。
ISO9001の審査で
“不良品発生(製造の不適合)”に対する
“原因”は一部の製造業を除いてかなり突っ込んだ
“原因追究”がなされていますが、
非製造業において、
よく出くわす“原因”として
“周知徹底不足”“教育不足”が多く、
特に笑えるのは(失礼!)“うっかりミス”ですね。
これらの“原因追究”で導き出したことが100%間違いとはいい
ませんが、平成17年4月25日に起きた死者107名に及んだ
JR西日本福知山線の運転士の事故原因が
“うっかりミス”だとしたらあなたはどう思われますか?
今回は、ここまでにしましょう。
次回は
原因追求の重要性を説明しますね。
最後までお読みいただき感謝!
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
あおいコンサルタント株式会社
運輸安全マネジメント推進協議会
山本昌幸(ISO9001・ISO14001主任審査員、行政書士、
特定社会保険労務士、運行管理者)
―――――――――――――――――――――――――
追伸(今回のオマケ):
先日、自動車のナンバープレートを盗難にあい、
約1か月後、「見つかった」と
少々遠くの
某警察署から電話があり、
確認のため、来署してほしいとのこと。
その数日後、警察署に向かい、
その際、接客スペースが使用中であったので、
刑事課の刑事さん:「すみません。では、こちらでお願いします」
と。
通された場所は、取調室。
刑事ドラマに出てくる部屋そのもので窓には鉄格子もありました。
でも、一応、私は遠方から来た「お客様扱い」でしたので。
“上座”に座らせていただきました。
「うん?でもこの席って、容疑者が座る方の席だよなぁ」
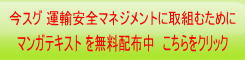 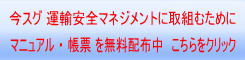
|

