第3回メールゼミ
こんにちは。
第3回目の「運輸安全マネジメント」メールゼミです。
今回は、
義務事項の「従業員への指導監督」の二つ目の
2 「方針」を実現するための「目標」の設定についてですね。
前回は、「方針」について説明しましたね。
覚えていますか?
「方針」の例としては、
*****輸送安全方針*****
1 当社は輸送の安全を第一とする
2 事故削減のための組織作りを目指す
3 事故削減のためにマネジメントシステムを
構築し運用、継続的に改善する
2008年4月1日 ○○運送株式会社 代表取締役 ○○□□
でしたね。
では、上記の「方針」の内容を実現するための「目標」について
説明しましょう。
まず、「目標」とは、事故削減・撲滅を実現するための
活動・・要するに運輸安全マネジメントを進めていく上での
「今年度の到達地点」と理解してください。
「目標」の事例としては
「今年度の自責事故発生件数を5件以下にする」 とか
「今年度の事故発生を対前年比20%減にする」 ですね。
「目標」を設定するうえでの注意点として、とにかく
その目標が“達成度判定可能であること”です。
運輸安全マネジメントはISO9001をベースに出来ていることは
ご存じだと思いますが、
ISO9001の“5.4.1品質目標”にも
“品質目標は、その達成度が判定可能で、
品質方針との整合が取れていなければならない” と
規定されています。
ですから、上記の「目標」の事例のように
期限到達時にその「目標」が達成したのか、しなかったのかが
判る「目標」であることが必要ですね。
達成度が判定できないようなあまりよくない「目標」の例としては、
「安全運転を実施する」 という目標でしょうね。
この目標では、“安全運転”の基準が不明ですよね。
基準が不明ですから、「目標」が達成したのかも評価できないです
ね。
では、“ナニ”をもって“安全運転”とするのかですね。
“安全運転”は、プロセス(過程)であり、その結果、
事故が減るのではないでしょうか。
では、その“事故が減る”という結果を判りやすく
「目標」にすればいいのです。ということで、
「今年度の自責事故発生件数を10件以下にする」
というような達成度判定可能な「目標」になりますね。
次に、すごく重要なことを説明しますね。
すごーく重要です!!!
運輸安全マネジメントを運用するうえで、
いや、マネジメントシステムを運用するうえで
重要なことは、
「ある事実をとらえた場合、その“根拠”と“展開”を確認する」
です。
「根拠を確認する」とは、その事実の「根拠はナニか?」と
遡って(過去にさかのぼる・遡及)確認することです。
また、「展開を確認する(そしてどうしたのか?)」とは、その事実
は「その後の展開はどうしたのか?」・・
要するに、その事実が未来に向かってどのように
運用や処理されているのかですね。
目標の例として、
「今年度の自責事故発生件数を10件以下にする」
という目標の「その根拠はナニか?」を考えてみましょう。
たとえば、昨年度の自責事故が14件発生していたので、
今年度は、4件減らして、10件と言う目標にしたのであればOKです
ね。
しかし、昨年度の事故が8件なのに、今年は10件の目標では、問題で
す。
また、昨年度の事故が10件で、今年も10件の目標では、
継続的改善の見地から考えると、やはり、良くないですね。
次に、「展開を確認する(そしてどうしたのか?」ですが、
前述の目標(自責事故10件以下)から
どのように展開されたのかを確認する必要があります。
自責事故を10件以下にするためにどのようなことをするのか?
そして、それが実現できているのか?
さらに、今年度終了時に目標は達成したのか・・・・・等々
これらが展開(未来に向かっての展開)ですね。
「ある事実をとらえた場合、その“根拠”と“展開”を確認する」は、
マネジメントシステムを運用していく上で
非常に重要ですので、是非、覚えてください。
また、マネジメントシステムだけではなく、
日常の業務でも、
「その根拠は?」
「そしてどうしたのか?(その後の展開)」を
常に意識して業務処理にあたってみてください。
次回の第4回目は、
「目標」を立案して、その「目標」を実現するための
「展開」である、
「措置(達成手段・行動計画)」についてお話ししましょう。
では、今回はこの辺で失礼します。
最後まで読んでいただき、感謝! です。
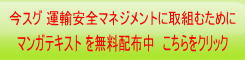 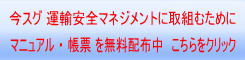
|

