第19回メールゼミ
こんにちは。
運輸安全.comの山本です。
第19回目の「運輸安全マネジメント」メールゼミです。
前回(18回)は、
「SHELモデル」を実際の事故事例にあてはめてみました。
今回は、その続きです。
実際の事故資料を国交省発表のものから引用しますね。
下のアドレスをクリックすると事故の詳細が表示されます。
http://www.unyuanzen.net/jikojirei1.html
この内容では、
事故要因:「車載してあったタイヤチェーンが未装着であった」
再発防止策:「乗客の安全を最優先した対策
(タイヤチェーンの装着等)を運転者に対して指導する」
ですね。
「SHEL」にあてはめますと、
「タイヤチェーン=H:Hardware(ハードウエア)」
「本人=L:Liveware(ドライバー本人)」
となります。
要するに
「L:本人」と「H:ハードウエア」の間に
“溝”があったことが問題のようです。
では、「L:本人」と「H:ハードウエア」の間にできた
“溝”
は、何のなのか?
「本人=L:Liveware(ドライバー本人)」
の雪道での対応の甘さと
「タイヤチェーン=H:Hardware(ハードウエア)」
の間にできた“溝”です。
そして、タイヤチェーンを未装着にしたのは
ドライバー本人ですから、そこで、
「なぜ、未装着にしたのか?」という発想も必要ですね。
それは、教育や指導が不足していたのではなく
「しくみ」が不足していたのではないでしょうか?
“ヒト”に責任があるのではなく“しくみ”に
責任があるという考え方です。
注意:
ここで誤解の内容に説明しますが、
「ヒューマンエラー」とは、
「ヒトだけが悪い」と言う事ではないですよ。
“しくみ”に責任があるとすれば、どのような責任でしょうか。
やはり、雪道走行におけるチェーン装着の
“基準”ではないでしょうか。
どのような雪道の場合はチェーンを装着するのか?
天候は? 時刻は? 路面の状態は?
降り始めからの時間は? 積雪量は?
積載(モノ、ヒト)の状態は? 道路は? などなど
そして、この“基準”について
教育や指導をする必要があります。
何も、この“基準”を
「雪道走行マニュアル」として、
マニュアルや手順書等の
文書にする必要は必ずしもありません。
必要な事は、会社において
雪道走行の基準(対策)を明確にして、
その内容をドライバーに守らせることですよね。
この“守らせる”ために、必要なのが
教育や指導となるのです。
ですから
「本人=L:Liveware(ドライバー本人)」
の雪道での対応の甘さと
「タイヤチェーン=H:Hardware(ハードウエア)」
の間にできた“溝”は、
雪道走行の基準(対策)を明確する
ですね。
仮に、既に雪道走行の基準(対策)が明確にされていたのであれば
なぜ、このドライバーは守ることが出来なかったのか。
その対策にしても、やはり、
“指導する”以外が必要と思われますが・・・。
次回は、運輸安全マネジメントの
重要部分である「マネジメントシステム」に戻していき、
「プロセス管理の重要性」を説明していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
あおいコンサルタント株式会社
運輸安全マネジメント推進協議会
山本昌幸(ISO9001・ISO14001主任審査員、行政書士、
特定社会保険労務士、運行管理者)
―――――――――――――――――――――――――
追伸(今回のオマケ):
次回から
「プロセス管理の重要性」を説明していきますが、
その予習として、
「プロセスってナニ?」の回答をチョット考えてみてください。
そして、「プロセス」の
前 と
後 にあることも。
よろしくお願いします。
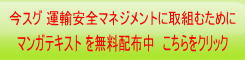 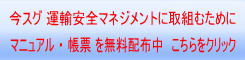
|

