第10回メールゼミ
こんにちは。
運輸安全.comの山本です。
第10回目の「運輸安全マネジメント」メールゼミです。
前回は、
“効果的”で“適切”である教育・研修を実施するためには
PDCAを活用しなくてはならないことを
説明しましたね。
PDCAの“P”・・
教育・研修のPlan:計画 を立案する場合は、
その
“根拠”が必要であることも説明しました。
“根拠”を考えるに当たりヒントになるのが
国交省の告示に書いてありましたね。
“・・対象となる従業員の
年齢、経歴、能力等に応じた具体的な計画・・”
今回は、
「年齢」「経歴」「能力」等を根拠にした
教育・研修の「P:Plan:計画」の立案方法を
前回より詳しく説明します。
その前に、「運輸安全マネジメント」のベースとなっている
ISO9001の教育・訓練の考え方を参考にしてみましょう。
ISO9001(JISQ9001)の“6.2.2力量,教育,訓練及び認識”の
要求事項を説明しますね
会社は、従業員ごとや、各役職、各職務に要求する
力量のハードルを設定する必要があります。
そして、各従業員をその力量のハードルに当てはめた結果、
ハードルに満たない従業員に対して、教育・訓練を計画し
(Plan)、(この計画が教育・訓練の「ニーズ」と言います)
実施し(Do)、その結果、従業員が力量のハードルを
超えることができたのかを検証し(Check)、
ハードルを越えられたのであれば、
更に力量アップのための施策を検討し(Act)、
ハードルを越えられなかったのであれば
“他の処置” (Act)をとらなくてはなりません。
“他の処置”とはどのようなものか説明します。
例えば、御社のドライバーで、C路線を担当するドライバーは
「フォークリフト免許」が必要だとしますね。
これば、会社がドライバーに要求した“力量のハードル”の
一つです(顧客からの要求事項でもありますね)。
この場合、このドライバーに「フォークリフト免許」を
取得させるための教育・訓練計画を立案します(Plan)。
そして、フォークリフト免許取得研修を受講させ(Do)、
免許取得ができたのかを確認します(Check)。
この事例は、ドライバーは会社が要求した力量のハードル・・・
つまり、「フォークリフト免許」を取得できたので
問題ありませんよね。
でも、もし、「フォークリフト免許」を取得できなかったなら・・・
“他の処置”が必要です。
“他の処置”の具体的事例として、
・他のドライバーにC路線を担当させる
・新しく、フォークリフト免許を保有しているドライバーを雇う
・C路線を他の業者に外注する
等などです。
この事例は、いわゆる“資格・免許”ですから
判りやすいのですが、
単なる“力量”“能力”だと、多少わかりづらいですが、
考え方は、まったく同じです。
この“他の処置”は、
ISO9001の目的である「顧客満足」を実現するためには
非常に重要ですね。
運輸安全マネジメントの目的である「事故の削減・撲滅」を
実現するためにも
非常に重要ですね。
では、話を戻して、
教育・研修計画の立案についてですが
ここで一つ質問です。
あなたの会社で次の
AさんとBさん、二人のドライバーが居たとしますね。
この、AさんとBさんの
教育・研修内容は同じでいいですか?
それとも、違う教育・研修が必要でしょうか?
Aさん:
年齢=40歳 運転歴=20年
事故歴=20年間ナシ 違反歴=20年間ナシ
Bさん:
年齢=63歳 運転歴=4年
事故歴=過去4年で物損事故2回、人身事故1回
違反歴=軽微の違反がたまにある、現在の減点は2点
Aさんは、いわゆる「優良ドライバー」ですね。
Bさんは・・・「中程度以下のドライバー」ですね。
この「優良ドライバー」であるAさんと
「中程度以下のドライバー」であるBさんが
同じ教育・研修では、ダメです。
もちろん、Aさん、Bさん同時に受けてもらう研修もありますが、
全ての教育・研修が同時ということは非常によくないことです。
そもそも、教育・研修を行うのには、
「目的」が存在します。
その「目的」は、
AさんとBさんとでは違いますから。
Aさんの教育・研修の目的の例としては
・今後も無事故無違反を継続してもらう
・模範ドライバーになるため
・より、生産性高い業務をおこなうため 等々
Bさんの教育・研修の目的の例としては、
・事故を二度と起こさないため
・違反を二度と起こさないため
・定年までの2年間問題なく就業してもらうため 等々
このように、同じ会社の同じ職種でも、
教育・研修の「目的」が違うわけですから
教育・研修の「内容」が違ってくるわけです。
また、先ほど説明したように、
Bさんの教育・研修を実施した結果、
その「目的」が果たせなかった場合は、
当然、“他の処置”が必要なのは言うまでもありませんね。
この、“他の処置”は、皆さんの会社の
社会や荷主さんに対する責任ですよね。
事故を起こすかもしれないドライバーを
そのまま、公道に出すのではなく、
教育・研修の結果、事故を起こさないようにさせたり、
教育・研修をしてもやはり無理であったら、
“他の処置”である、
他のドライバーに変えたり、
その業務を外注に出すことが必要でしょう。
教育・研修についても
PDCAが必要であり、
教育・研修には、「実施目的」があることを
ご理解ください。
次回は、教育・研修の
種類を説明します。
では、今回はこの辺で失礼します。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
あおいコンサルタント株式会社
運輸安全マネジメント推進協議会
山本昌幸(ISO9001・ISO14001主任審査員、行政書士、
特定社会保険労務士、運行管理者)
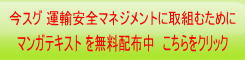 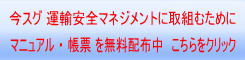
|

